みなさまどうも、わさびうしです。
猛暑から一転、一気に秋の涼しさを感じる一日となりました。体調管理にはどうぞお気を付けください。猛暑さんはもう戻ってこなくていいです。
過熱していた日本市場も、日銀のETF売却方針を受け一時は800円あまり下落しました。
19日の日経平均株価は、日銀の金融政策決定会合で、株式市場の安定化を目的に購入してきたETF=上場投資信託の売却が決まったことで、一時800円余り下落し、4万5000円を割り込む場面がありました。
引用:テレ東BIZ
結局終値は257円安の45,045円に落ち着きましたが、9月は権利確定月の銘柄も多く、市場も少々涼しくなる時期かもしれませんね。
秋のPF(ポートフォリオ)を見直し月間
少し前に「9月はお金の整理月」という記事を投稿しました。
家計を中心とした節約チャレンジがメインの内容でしたが、せっかくなので自身のPFも見直してみました。
結論から言いますと、このたびSBI証券の特定口座で保有しているインデックスファンドをすべて売却することにしたのです。
わさびうしの投資方針おさらい
インデックス売却のお話に入る前に、ちょっとおさらいです。
私の投資方針は基本的に「分散投資・長期運用」です。
SBI証券のNISA積み立て枠で毎月一定額をインデックス購入、成長投資枠は国内株を単元未満でスポット購入しています。
楽天証券の特定口座はほぼ米国株専用となっており、高配当個別株、ETF、インデックスをスポット購入。こちらはリバランスや再投資のための利確をスイングトレードで行うこともあり、ややアクティブな運用傾向が強くなっています。
これらはあくまで「基本」方針であり、例外的な売買を実施することも珍しくはありません。ある程度の臨機応変さは必要だと考えています。
特定口座インデックス売却の経緯
特定口座に居座るインデックスファンドたち
私が例外的に保有していたのが、SBIの特定口座に居座るインデックスファンド達です。
かなり古い記事にはなりますが、当時の保有ファンドのデータは以下の通りです。
せっかくなので現時点(9/19)と比較してみました。
| ファンド名 | 保有口数 | 評価額 | 取得金額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 4,219口 | 11,868円 | 10,000円 | +1,868円 (+18.68%) |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 629口 | 4,663円 | 4,000円 | +663円 (+16.58%) |
| [VYM]SBI・V・米国高配当インデックス(年4回決算型) | 2,728口 | 3,197円 | 3,000円 | +197円 (+6.57%) |
| [SCHD]SBI・S・米国高配当インデックス(年4回決算型) | 27,474口 | 25,267円 | 25,839円 | -572 (-2.21%) |
| 合計 | 44,995円 | 42,839円 | +2,156円 (+5.03%) |
| ファンド名 | 保有口数 | 評価額 | 取得金額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 4,219口 | 12,600円 (※取引金額) | 10,000円 | +2,600円 (+26.00%) |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 629口 | 5,046円 | 4,000円 | +1,046円 (+26.15%) |
| [VYM]SBI・V・米国高配当インデックス(年4回決算型) | 4,357口 | 5,371円 | 5,000円 | +371円 (+7.42%) |
| [SCHD]SBI・S・米国高配当インデックス(年4回決算型) | 27,474口 | 26,185円 | 25,839円 | +346円 (+1.34%) |
| 合計 | 49,202円 | 44,839円 | +4,363円 (+9.73%) |
さほど追加資金は投入していませんが、1ヵ月半で含み益はほぼ倍増しており、悪くない成績だと思います。VYM、SCHDについては再投資型ではなく受取型にしていたので、少額ではありますが分配金をいただいていました。
特定口座インデックス売却の理由
インデックスファンドの運用の主流は「長期運用」です。保有が長ければ長いほど恩恵は大きく、※ドルコスト平均法を用いることで評価額も安定します。
※ドルコスト平均法:資金を分割し定期的に購入する投資法。会話中に普段使いできると賢く見える。
データが示すように、私もその恩恵を少額、短期ながら感じることができました。定期購入ではありませんが、タイミング投資で安値買いすることで、よりお得感は増していたと思います。
にもかかわらず、今回「すべて売却する」という決断にいたったのは――NISA枠の存在です。
NISA枠にまだ余裕がある
もともと「年内に枠を使い切ってしまうのでは?」という計算が最初にあったので、安値の内にあらかじめ特定口座に一定額を仕込もうと考えていました。
しかし夏場以降に休職したこともあり、入金力は停滞の一途を爆進中。積立枠・成長投資枠の年内満額利用も見込めなくなってしまいました。

これが大きな理由です
特定口座は配当金だろうが含み益だろうが、その利益に20.315%(※所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかってしまいます。
※復興特別所得税(0.315%)上乗せは2037年までの予定。信じてるぞ日本政府。
一方ご存じNISA枠で生じた利益はすべて非課税(国内は)。これをいかさない手はありません。
というのが、理論上の理由です。
実際のところ
なんかね、特定口座に堂々と居座られてるのが嫌だったんですよ。管理するのもややこしいし、ページ圧迫されるの少々ストレスだったので。
購入したのは私だし、なんならオルカンは成長枠で買ったと思ったら間違えて特定になってただけなので、完全に自分のポカなんですよね。
しかし日々視界に入る保有ファンド達から「え、売るの?今売るの?税金かかるよ?」「ほれほれ、ワシら売ったら評価額下がるで~」と見下されているような気がして……
キミたち安心してるよね?私が売らないと思ってるよね?舐めてるよね?

いいよやってやんよオラァ!(売却ポチッ)
と勢いで売っちゃった面もちょっとだけあります。
ですので今回の売却は感情2割、理論8割くらいで決断を下した感じですね。
まとめ:時には思い切った売却も必要
今回は特定口座のインデックス売却についてのお話でした。売却益に税金が生じる分、短期的に評価額は下がるのは致し方ありませんね。
ですが、長期的な視点で考えるとNISA枠への移行を決断したことは決して間違ってはいないはず。我ながら冷静な判断ができたと思います。
株式は購入と比べて売却のタイミングの方が難しいと言われています。高配当株や優待株で予想外の含み益が生じた場合には、なかなか売却に踏み切れないことも多いのではないでしょうか。

利確のタイミング、迷いますよね
「今から出口戦略を考えても損はない」と言いたいところですが、私はまだまだ投資1年生。まずは黙って基本のバイ&ホールド。いつも心に「JUST KEEP BUYING」です!

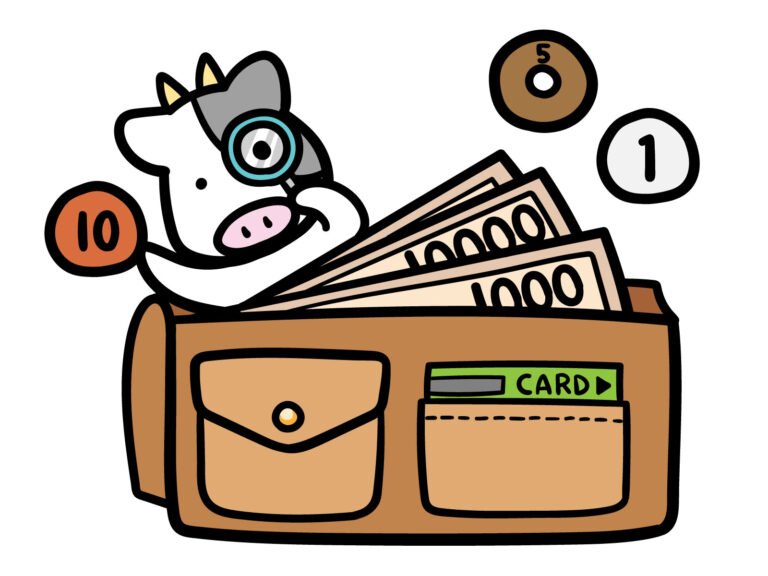





コメント